
「Webサイト制作、何から手をつければ良いか分からない…」そんな方へ。Webサイトにおける要件定義の重要性をご存知ですか?
こんな悩みを抱えていませんか?
実は、Webサイト制作における要件定義の重要性は非常に高く、プロジェクト成功の9割を決めると言われています。
要件定義が曖昧なまま進めると
・制作費用が予算の1.5〜2倍に膨らむ
・納期が2〜3ヶ月遅れる
・完成しても成果が出ない「幽霊サイト」になる
このようなリスクが高まります。
この記事では、100社以上のWeb制作に携わってきたプロが、Webサイトにおける要件定義の重要性から具体的な進め方、制作会社との円滑なコミュニケーション術まで、すべて解説します。
Webサイト制作における要件定義とは?その重要性を解説
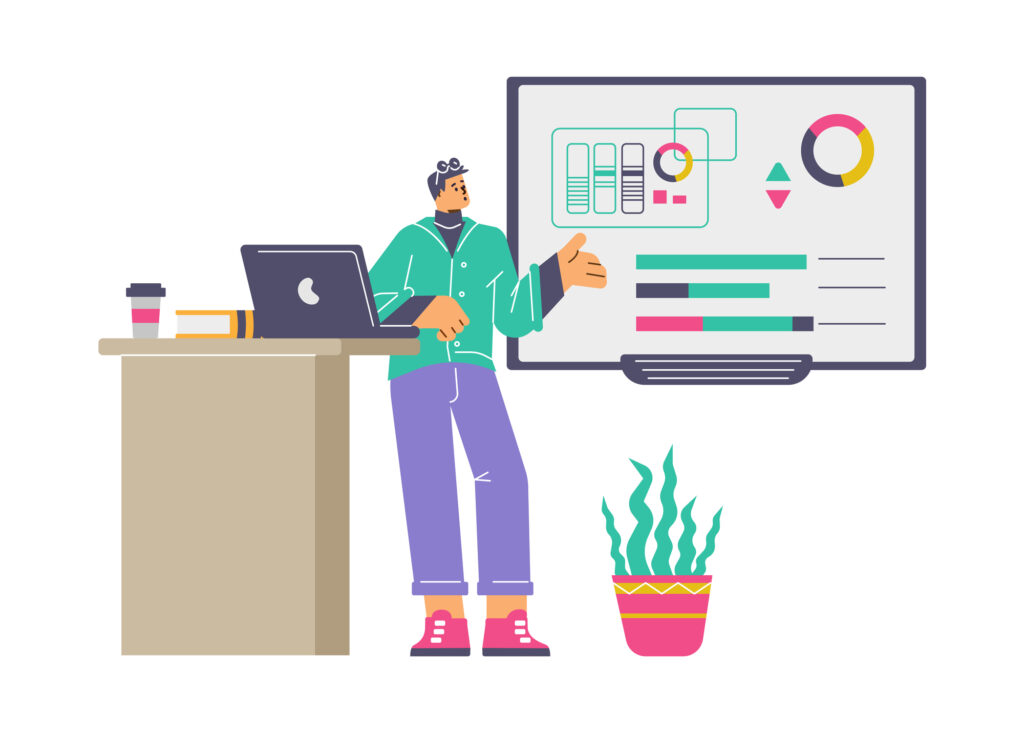
要件定義とは、Webサイト制作の「設計図」を作る工程です。 サイトの目的、必要な機能、デザインの方向性などを明確にし、関係者全員の認識を合わせます。この設計図があることで、正確な見積もりが可能になり、開発中の手戻りを防ぎます。Webサイトにおける要件定義の重要性を理解することが、プロジェクト成功の第一歩となります。
要件定義はWebサイトの羅針盤となる設計図
では具体的にどのようなことを決めるのでしょうか。
要件定義では「誰が、何を、なぜ、どのように作るのか」を明確化します。Webサイトも目的・機能・仕様・デザインの方向性を言語化・資料化することが不可欠です。
関係者の認識ずれを防ぎ、正確な見積もりと手戻りのない開発を実現することができます。特に近年は、API連携やセキュリティ対策など技術要件が複雑化しており、Webサイトにおける要件定義の重要性がさらに高まっています。このような状況だからこそ、全員の認識を合わせる要件定義は、プロジェクト成功の生命線となっているのです。
【失敗事例から学ぶ】要件定義の不備が招く3つの失敗パターン
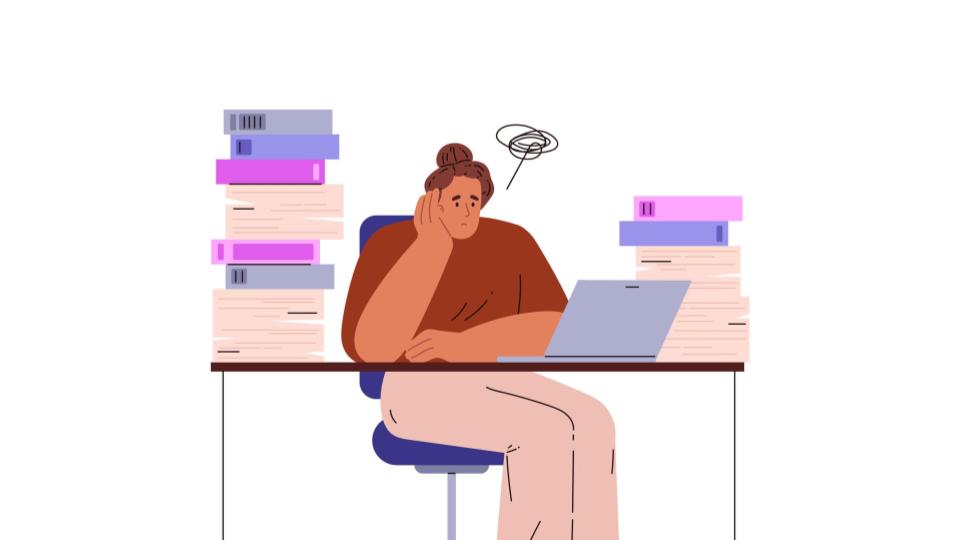
Webサイト制作における要件定義の重要性をより深く理解するために、実際に見聞きした典型的な失敗パターンと、その改善策を紹介します。これらの事例から、要件定義の重要性を実感していただけるはずです。
ケース1:目的が曖昧で誰も使わないサイトが完成
見た目は美しいサイトが完成。しかし「なぜリニューアルするか」「誰のどんな課題を解決するか」など目標が曖昧なまま進行。KPIも未設定で、社内の合意形成も不足していました。結果、お問い合わせは増えず、社内の誰も更新しない「作っただけのサイト」に。リニューアル費用が無駄になっただけでなく、チームの士気も大きく低下してしまいました。
この失敗を防ぐには
プロジェクト開始前に、具体的なKGI/KPIを設定することが必須。ペルソナを明確化して解決すべき課題を特定。経営層を含めた全関係者で目的をしっかり合意しましょう。
ケース2:仕様の認識齟齬で予算オーバー&納期遅延
思い込みで詳細仕様を詰めず、「よしなに作ってください」と開発を進めました。その結果、終盤に「思っていたのと違う」が発覚しました。
例えば「お問い合わせフォーム」一つでも仕様は多岐にわたります。自動返信メールの有無、CRM連携、スパム対策などです。要件定義書も作成していませんでした。
大規模な手戻りが発生しました。予算は1.5倍に膨らみ、納期は3ヶ月遅延しました。
この失敗を防ぐには
機能ごとの仕様を文書化し、ワイヤーフレームでのイメージ共有が重要です。必ず要件定義書を作成し、発注者・制作会社の双方が内容を確認して合意しましょう。
ケース3:運用が考慮されず公開後に更新が止まる
「公開後の運用」を検討せず、更新担当者のスキルレベルも確認しないまま制作を進めた結果、ブログ投稿が複雑すぎてWeb担当者が更新できない仕様に。CMS選定も失敗していました。お知らせ欄は放置され、古い情報が残ったまま。ユーザーの信頼を失い、SEO評価も低下してしまいました。
この失敗を防ぐには
公開前に、誰が・いつ・どのように更新するかを明確に決めておきましょう。担当者のスキルに合わせてCMSを選定し、マニュアル作成と運用トレーニングを実施することで、スムーズな運用が可能になります。
網羅版!Webサイト要件定義で決めるべき全10項目

要件定義の重要性は理解できても、「実際に何から手をつければいいの?」と悩む方は多いはずです。そこで、Webサイトにおける要件定義の重要性を実現するために、ここからは実務で必ず押さえるべき10項目を、具体例を交えて詳しく解説します。このチェックリストに沿って進めることで、抜け漏れのない要件定義が可能になります。
1. プロジェクトの目的とゴール設定(KGI/KPI)
Webサイトで何を達成したいのか、最終ゴール(KGI)と、それを達成するための中間指標(KPI)を具体的に設定します。つまり、「なぜWebサイトを作るのか」という根源的な問いに答える、すべての土台となる項目です。この項目の重要性は、要件定義全体の成否を左右します。
KGIの例
ECサイトの売上を前年比120%向上
採用サイトからの応募者数を年間100名獲得
KPIの例
月間のお問い合わせ数100件
特定サービスページのセッション数 月間1万
ホワイトペーパーのダウンロード数 月間500件
【ポイント】必ず数値化し、測定可能な目標を設定しましょう。曖昧な目標は、プロジェクトの迷走を招きます。
2. ターゲットユーザーとペルソナの具体化
「誰に」情報を届けたいのかを明確にします。年齢・性別・職業だけでなく、価値観、ライフスタイル、抱えている課題まで掘り下げた「ペルソナ」を作成することで、ターゲットに響くコンテンツやデザインが見えてきます。
ペルソナ設定の例
・都内在住の30代女性、共働きの母親
・時短家事に強い関心がある
・情報収集は主にスマホ(SNS・情報サイト)
・週末に家族との時間を大切にしたい
・信頼できる情報源を求めている
3. カスタマージャーニーマップによる体験設計
設定したペルソナが、どのような経緯でサイトを訪れ、サイト内でどのように行動し、最終的にコンバージョン(目標達成)に至るのか。その一連のプロセスを時系列で可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。これにより、ユーザーが各接点で何を考え、何を感じ、どんな情報を求めているかを分析でき、最適なコンテンツや機能、導線を設計することができます。
4. サイト全体の構成(サイトマップとディレクトリ構造)
Webサイトに必要なページを全て洗い出し、その関係性を整理したサイトマップを作成します。ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるか、というユーザビリティの視点はもちろん、論理的な情報構造は検索エンジンにも評価されやすく、SEO対策の観点からも非常に重要です。また、トップページから下層ページへの階層構造(ディレクトリ構造)も、シンプルで分かりやすいものに設計します。
5. 各ページに必要な機能要件の定義
お問い合わせフォーム、ブログ機能(CMS)、会員登録・ログイン機能、オンライン決済、資料ダウンロード、サイト内検索など、サイトの目的を達成するために必要な機能を具体的に定義します。ただし注意が必要です。この際、「この機能は本当に必要か?」を常に見極め、過剰な仕様にならないように優先順位(Must/Want/Nice to have)をつけることも大切です。そうすることで、予算内で最大限の効果を出すことが可能になります。
6. 見落とし厳禁!サイトの品質を左右する非機能要件
機能要件が「何ができるか」を定義するのに対し、非機能要件は「どのように動くか」というシステムの品質に関する要件です。実は、ユーザー体験やサイトの信頼性に直結するため非常に重要な要素ですが、残念ながら、見落とされがちな項目でもあります。Webサイトの要件定義において、非機能要件の重要性は非常に高いため、意識的にチェックする必要があります。
パフォーマンス : ページの表示速度、レスポンスタイム
セキュリティ : SSL化、脆弱性対策、不正アクセス防止
( 参考: IPA 情報処理推進機構|セキュリティ対策)
可用性 : サーバーの稼働率、障害発生時の復旧時間
ユーザビリティ/アクセシビリティ :操作のしやすさ、誰にとっても使いやすいデザイン
(参考: デジタル庁|ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック)
拡張性 : 将来のアクセス増や機能追加への対応力
7. ブランドイメージを体現するデザインとトンマナ
Webサイトのデザインの方向性やトーン&マナー(トンマナ)を決定します。これには、ロゴの扱い、使用する色(カラーパレット)、文字の書体(タイポグラフィ)、写真やイラストの雰囲気、文章の口調まで含まれます。企業のブランドイメージやターゲットユーザーの好みに合わせることが重要で、参考サイトを複数挙げて「このサイトの雰囲気は好き」「このサイトのこの部分は避けたい」といった形でイメージを共有すると認識のズレを防げます。
8. コンテンツ要件と素材の準備計画
各ページに掲載する具体的なコンテンツ(テキスト、画像、動画など)の要件を定義します。誰が、いつまでに、どのような内容の原稿や素材を準備するのか、その担当者とスケジュールを明確にしておく必要があります。特に、既存サイトからのコンテンツ移行がある場合は、その範囲と方法も決めておきましょう。素材の準備遅れは、プロジェクト全体の遅延に直結する大きな要因です。
9. 安定稼働を支えるインフラとサーバー要件
Webサイトを公開するためのドメインやサーバーをどうするかを決めます。予想されるアクセス数やセキュリティ要件、利用するシステムに応じて、適切なスペックのサーバー(共用サーバー、VPS、クラウドサーバーなど)を選ぶことが、サイトの安定稼働につながります。また、将来の事業拡大を見越して、アクセスが増えても対応できる拡張性(スケーラビリティ)も考慮しておくと良いでしょう。
10. 公開後の成長戦略となる運用・保守体制
Webサイトは公開してからが本当のスタートです。「誰が」「いつ」「どのように」コンテンツを更新していくのか、システムのアップデートやセキュリティ対策、万が一のトラブルにどう対応するのかなど、公開後の運用・保守体制をあらかじめ具体的に決めておく必要があります。これを怠ると、せっかく作ったサイトが陳腐化し、セキュリティリスクに晒されることになります。
失敗しない!要件定義書の具体的な書き方とテンプレート

要件定義で決定した内容は、必ず「要件定義書」というドキュメントにまとめ、関係者全員の共通認識とします。要件定義書の作成は、Webサイトプロジェクトにおける要件定義の重要性を具現化する作業です。ここでは、その具体的な書き方と盛り込むべき項目を解説します。
なぜ要件定義書というドキュメントが必要なのか
口頭での確認や議事録だけでは、後から「言った、言わない」のトラブルに発展するリスクがあります。要件定義書は、プロジェクトの公式な「設計図」であり、「契約書」の一部とも言える重要なドキュメントです。
・関係者間の認識のズレをなくす
・プロジェクトのスコープ(範囲)を明確にする
・開発の指針となり、品質を担保する
・仕様変更や追加要件の判断基準となる
・後任担当者への引き継ぎ資料となる
このように、要件定義書はプロジェクトを円滑に進め、クライアントと制作会社の双方を守るために不可欠なのです。
要件定義書に盛り込むべき必須項目一覧
1.プロジェクト概要: 背景、目的、ゴール(KGI/KPI)、ターゲット、スコープ(対応範囲)
2.サイトマップ: 全てのページ構成と階層構造
3.機能要件一覧: 機能名、概要、詳細仕様、実装の優先順位
4.非機能要件: パフォーマンス、セキュリティ、可用性などの具体的な目標値
5.画面設計: ワイヤーフレーム(各ページのレイアウト設計図)、画面遷移図
6.コンテンツ要件: 各ページのコンテンツ概要、素材(原稿・画像)の準備担当と納期
7.デザイン要件: トーン&マナー、カラー、フォント、参考サイト
8.インフラ・開発環境: ドメイン、サーバー、使用する言語やCMS
9.運用・保守要件: 更新体制、保守範囲、緊急時の連絡体制
10.プロジェクト体制とスケジュール: 関係者リスト、役割分担、各工程のマイルストーン
作成時に役立つフレームワークとツール紹介
要件定義を効率的かつ論理的に進めるために、様々なフレームワークやツールが役立ちます。
【5W1H】: 「Why(なぜ)」「What(何を)」「Who(誰が)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「How(どのように)」を明確にすることで、要件の抜け漏れを防ぎます。
【マインドマップ】: 中心となるテーマから関連する要素を放射状に広げていく思考ツール。アイデアの洗い出しや情報の整理に役立ちます。(例:XMind, MindMeister)
【ワイヤーフレーム作成ツール】: 画面のレイアウトを視覚的に設計できます。
Cacoo – 日本製で直感的に使いやすい
Figma – 無料で使える業界標準ツール
Adobe XD – Adobe公式の高機能ツール
プロが実践する要件定義を成功に導く4ステップ
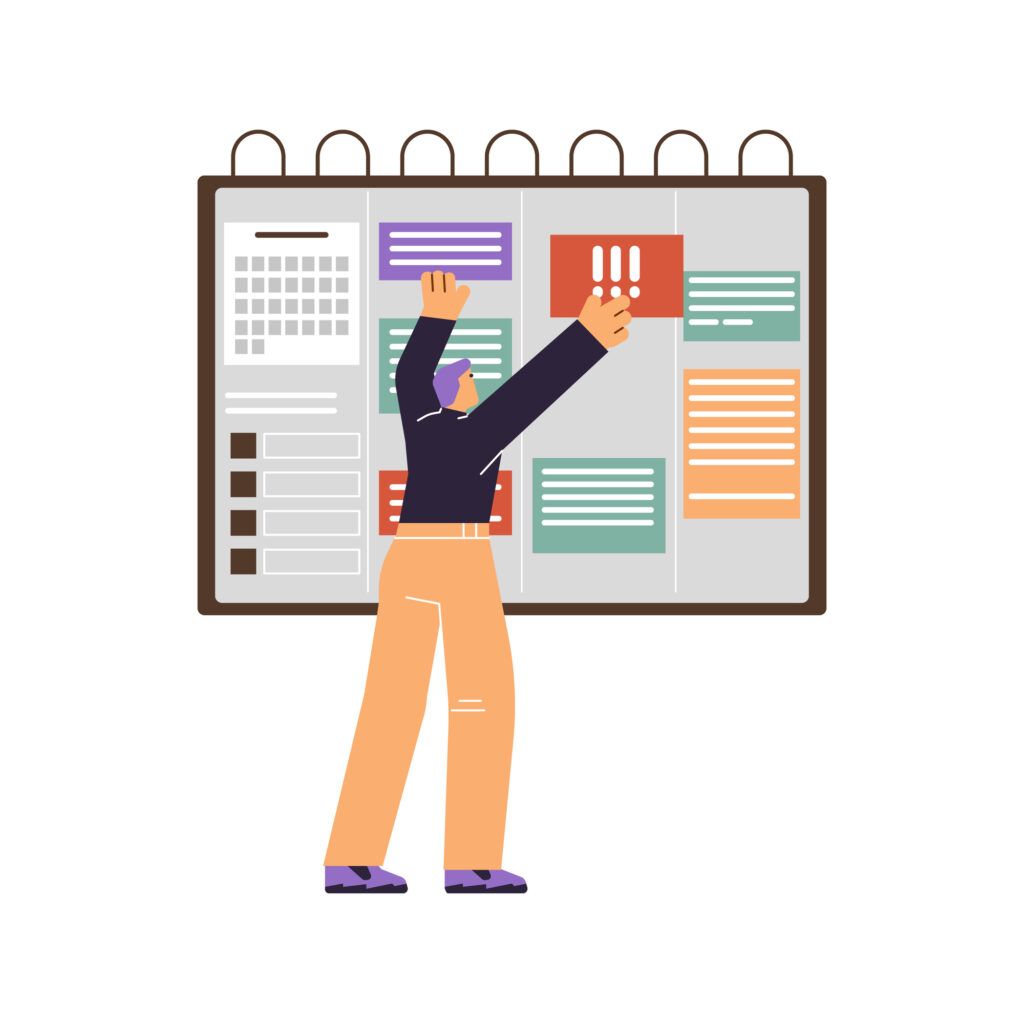
私たちフロンティアエージェンシーが、どのように要件定義を進めているのか、その具体的なステップを紹介します。このプロセスを経ることで、お客様のビジネスを成功に導くWebサイトの土台を築きます。
STEP1:徹底的なヒアリングと多角的な現状分析
まず、お客様のビジネスが抱える課題、Webサイト制作の目的、事業計画などを徹底的にヒアリングします。同時に、既存サイトがある場合はアクセス解析データやヒートマップ分析、競合サイトの調査や市場の分析(3C分析、SWOT分析など)を行い、客観的な視点からプロジェクトの成功要因を探ります。経営層から現場の担当者まで、関係部署の主要な方々へのインタビューも欠かせません。
STEP2:フレームワークを用いた要件の洗い出しと整理
ヒアリングと分析で得た情報をもとに、Webサイトに必要な機能やコンテンツなどの要件を網羅的に洗い出します。この際、マインドマップなどを使って発散的にアイデアを出し尽くすのが効果的です。その上で、「Must(必須)」「Want(希望)」「Nice to have(あれば嬉しい)」のように優先順位をつけ、予算や納期とのバランスを考慮しながら整理します。この優先順位付けが、現実的で効果の高い計画を立てる上で非常に重要です。
STEP3:認識のズレを防ぐ要件定義書の作成
整理した内容を、前述の項目を網羅した「要件定義書」というドキュメントにまとめます。このドキュメントには、決定した全ての項目を詳細に、かつ誰が読んでも誤解が生じないように具体的に記載します。ワイヤーフレーム(画面の設計図)や機能一覧、非機能要件(表示速度やセキュリティなど)も含まれます。これがプロジェクトの公式な「設計図」となります。
STEP4:関係者全員によるレビューと合意形成
作成した要件定義書をもとに、お客様を含む全てのプロジェクト関係者と最終的な認識合わせ(レビュー会)を行い、内容の承認を得ます。この段階で疑問点や懸念点を全て解消し、全員が納得した上でプロジェクトをスタートさせることが極めて重要です。ここでしっかりと合意形成を行うことで、プロジェクト開始後の「言った言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。
Webサイト要件定義の成功確率を格段に上げる3つの秘訣

最後に、要件定義をよりスムーズに、そして確実に成功させるための秘訣を3つ紹介します。これらを意識するだけで、プロジェクトの質は大きく向上するでしょう。
1. 関係者全員を初期段階で巻き込み「自分ごと化」させる
Webサイト制作は、特定の部署だけで完結するものではありません。意思決定者である経営層から、日々の業務でサイトを利用する現場の担当者まで、関連する全てのメンバーをプロジェクトの初期段階から巻き込むことが成功の鍵です。これにより、多角的な視点を取り入れられるだけでなく、各々に当事者意識が芽生え、「自分たちのサイトを成功させる」という協力的な体制が生まれます。
2. 表面的な要望の奥にある本質的な課題を深掘りする
「この機能が欲しい」「こんなデザインにしたい」という表面的な要望の奥にある、本質的な目的や課題を探ることが重要です。有名な「Why-Why分析(なぜなぜ分析)」のように、「なぜその機能が必要なのですか?」と問いを5回繰り返すことで、より効果的な解決策が見つかることがあります。例えば、「ブログ機能が欲しい」→「なぜ?」→「情報発信したい」→「なぜ?」→「専門性を示して潜在顧客からの信頼を得たい」というように、本質的なゴールが見えてくれば、ブログ以外の選択肢(例:導入事例コンテンツ、ホワイトペーパー)も検討できるのです。
3. 経験豊富なWeb制作会社の知見を最大限に活用する
自社の視点だけでは、見落としてしまう課題や最適な解決策に気づけないことがあります。数多くのWebサイト制作を手掛けてきたプロフェッショナルは、最新の技術動向や成功事例、そして避けるべき落とし穴を熟知しています。制作会社を単なる「作業者」としてではなく、ビジネスを成功に導く「パートナー」として捉え、その客観的な視点や知見を積極的に活用することが、プロジェクトを成功へと導く最短ルートです。遠慮せずに疑問をぶつけ、専門的なアドバイスを求めましょう。
まとめ

この記事では、Webサイトにおける要件定義の重要性について、その全体像から具体的な進め方まで網羅的に解説しました。
Webサイト要件定義の重要性をまとめると
・プロジェクト成功の9割を決める「設計図」
・予算超過・納期遅延を防ぐ
・関係者の認識を統一する
・ビジネスの成果に直結する
要件定義はプロジェクトの成功を左右する「設計図」であり、ビジネスの成果に直結する最重要工程です。
Webサイト制作における要件定義の重要性を理解し、この工程を丁寧に行うことで、プロジェクトの成功確率が格段に上がります。 この工程が曖昧なままでは、目的からズレたサイトが完成しかねません。失敗を避け、ビジネスを成功に繋げるためにも、目的やターゲットを明確化し、関係者間でしっかりと合意形成することが重要です。 もしWebサイトの要件定義にお悩みでしたら、その重要性を熟知したプロに相談してみてはいかがでしょうか。
【参考資料】本記事の作成にあたり、以下の公的機関・ツールを参考にしています。
▼ セキュリティ対策
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構|セキュリティ対策情報
▼アクセシビリティ
デジタル庁|ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック
▼要件定義ツール
Figma ワイヤーフレーム作成ツール
Adobe XDデザイン・プロトタイプツール
Cacoo オンライン作図ツール
▼統計・DX推進
総務省|情報通信統計
経済産業省|デジタルトランスフォーメーション推進
【関連記事】
Webサイト制作に関するこちらの記事もおすすめです。
▼ホームページで集客できない3つの原因とは?今日からできる改善策をプロが徹底解説
▼ホームページリニューアルの必要性を判断 成功のポイントを徹底解説
▼ホームページ制作期間の目安は?種類別スケジュールと短縮する5つのコツ【2025年最新】
